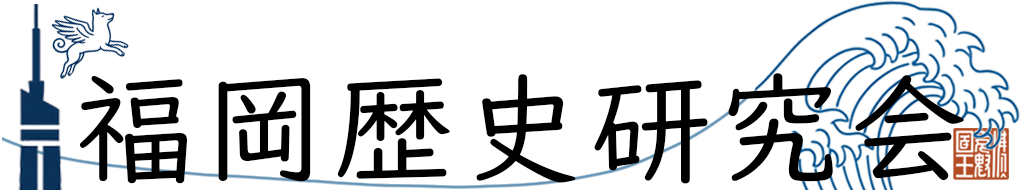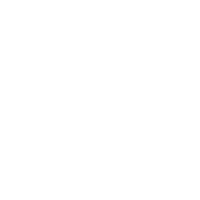石瀧 豊美(いしたき・とよみ)氏
 石瀧 豊美氏 |
イシタキ人権学研究所所長・福岡地方史研究会会長
 イシタキ人権学研究所
イシタキ人権学研究所
1949年、福岡市生まれ。自治体史の編纂や自治体講座、出版活動など広く活躍。平成24年度には福岡市文化賞を受賞。 最新著作は、戦前から戦後にかけての頭山満の活動を、日中和平の視点から見つめ直す意欲的な一冊。2025年には続編新著を発表予定。 ──主な著書・編著── 『近代福岡の歴史と人物―異・偉人伝―』(2009年 イシタキ人権学研究所) 『玄洋社・封印された実像』(2010年 海鳥社) 『筑前竹槍一揆研究ノート』(2012年 花乱社) ──共著・編著── 自治体史共編著「新修 福岡市史」内 『資料編 近現代1 維新見聞記』(2012年) 『特別編 福岡城 築城から現代まで』(2013年) 編著『博多謎解き散歩』(2014年 新人物文庫) 『頭山満・未完の昭和史 ― 日中不戦の信念と日中和平工作』(2023年 花乱社) |
|---|
浦辺 登 (うらべ・のぼる)氏
 浦辺 登氏 |
歴史作家・文芸評論家・書評家
 浦辺登 公式サイト
浦辺登 公式サイト
 一般社団法人 もっと自分の町を知ろう
一般社団法人 もっと自分の町を知ろう
1956年(昭和31年)福岡県筑紫野市生まれ。福岡大学人文学部ドイツ語学科卒業。 福岡の近現代史、明治・大正・昭和の変化期、人物史や地域史を広く取り上げ、連載や地域の歴史講演会、講座への登壇も多数。 『想い出の汀』などでは「書評の鉄人」の異名を遺憾なく発揮し、常に新たなテーマを読者・参加者と共に探求している。 ───主な著書─── 『太宰府天満宮の定遠館―遠の朝廷から日清戦争まで』(2009年 弦書房) 『霊園から見た近代日本』(2011年 弦書房) 『東京の片隅からみた近代日本』(2012年 弦書房) 『アジア独立と東京五輪―「ガネホ」とアジア主義』(2013年 弦書房) 『玄洋社とは何者か』(2017年 弦書房) 『勝海舟から始まる近代日本』(2019年 弦書房) ───共著・編著─── 『権藤成卿の君民共治論』(2019年、展転社) 『福岡地方史研究』第56・57号(花乱社、2018〜2019年) 雑誌『維新秘話福岡』(花乱社、2020年)など |
|---|
有馬 学(ありま・まなぶ)氏
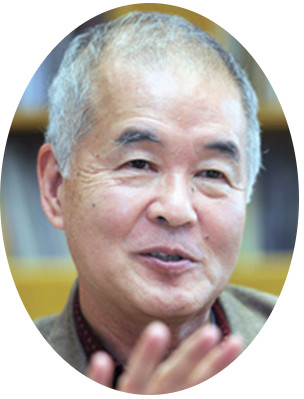 有馬 学氏 |
日本近代史研究者・九州大学名誉教授 / 前福岡市博物館長
1945年、北京生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程満期退学。 1976年、九州大学文学部講師に着任し、助教授・教授を経て、1994年より大学院比較社会文化研究院教授。2009年に定年退職し、九州大学名誉教授となる。 2012年4月から2024年3月まで12年間福岡市博物館長を務め、文化庁文化審議会史跡分科会委員、日韓歴史共同研究委員、日本の産業革命遺産世界遺産登録推進協議会専門家委員、福岡市史編集委員長などを歴任。地域史や産業遺産の保存において、中心的な役割を担っている。 ──主な著書── 『帝国の昭和』(2010年 講談社 学術文庫) 『日本の近代4「国際化」の中の帝国日本』(2013年 中公文庫) 『「戦後」を読み直す ― 同時代史の試み』(2024年 中公選書) ──共著・編著── 『写真経験の社会史』(共著 2012年 岩田書院) 『近代日本の企業家と政治 ― 安川敬一郎とその時代』(編著 2009年 吉川弘文館) |
|---|
河村 哲夫(かわむら・てつお)氏
 河村 哲夫氏 |
歴史作家・福岡県文化団体連合会参与
1947年、福岡県柳川市生まれ。九州大学法学部卒業。 立花壱岐研究会、日本ペンクラブ会員としても知られ、長年にわたり九州の歴史と風土に深いまなざしを向けた著書多数。 講義では、「古事記」や「日本書紀」のみならず、地域に伝わる言い伝えや社伝、考古学の成果を踏まえ、多角的な視点から歴史の真実に迫る。平成24年度は「神功皇后伝承」、25年度は「景行天皇伝承」、26年度にはさらに時代をさかのぼり「神武天皇伝承」をテーマに講義。古代日本の成立を紐解く壮大な歴史の旅へと誘っている。 ──主な著書── 立花宗茂を描く 『志は、天下』(1995年 海鳥社) 『立花宗茂』(1999年 西日本新聞社) 『柳川城炎上』(1999年 角川書店) 神功皇后の足跡をたどる 『西日本古代紀行 ~神功皇后風土記~』(2001年 西日本新聞社) 『筑後争乱記』(2003年 海鳥社) 古代天皇の巡幸がテーマ 『九州を制覇した大王 ~景行天皇巡幸記~』(2006年、海鳥社) 『天を翔けた男』(2007年 梓書院) 『龍王の海・国姓爺・鄭成功』(2010年 海鳥社) 『天草の豪商・石本平兵衛』(2012年 藤原書店) 『神功皇后の謎を解く ~伝承地探訪録~』(2013年 原書房) 『景行天皇と日本武尊 列島を制覇した大王』 (2015年 原書房) |
|---|
西谷 正(にしたに・ただし)氏
 西谷 正氏 |
考古学者・九州大学名誉教授
1938年、大阪府高槻市生まれ。京都大学大学院修士課程修了後、奈良国立文化財研究所、福岡県教育委員会を経て、九州大学で助教授・教授を務める。 平城宮跡をはじめ国内各地の遺跡調査に携わるほか東アジア各地で現地調査を実施。ソウル大学への留学経験を生かし、国際的な視野に立った考古学研究を展開。 邪馬台国の「近畿説」を唱える研究成果を発表。2003年に第62回西日本文化賞を受賞。 現在は海の道むなかた館長、九州歴史資料館名誉館長、伊都国歴史博物館名誉館長を務め、後進の指導と地域文化の発信に力を注ぐ。 ──主な著書── 『韓半島考古学論叢』(2002 すずさわ書店) 『東アジア考古学辞典』(2007 東京堂出版) 『東アジアの巨大古墳』(共著 2008 大和書房) 『魏志倭人伝の考古学 ─ 邪馬台国への道』(2009 学生社) 『古代北東アジアの中の日本』(2010 梓書院) 『古代の日本と朝鮮半島の交流史』(2014 同成社) |
|---|
丸山 雍成(まるやま・やすなり)氏
 丸山 雍成氏 |
交通史研究者・九州大学名誉教授
1945年、北京生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程満期退学。 1976年、九州大学文学部講師に着任し、助教授・教授を経て、1994年より大学院比較社会文化研究院教授。2009年に定年退職し、九州大学名誉教授となる。 2012年4月から福岡市博物館長を務め、文化庁文化審議会史跡分科会委員、日韓歴史共同研究委員、日本の産業革命遺産世界遺産登録推進協議会専門家委員、福岡市史編集委員長などを歴任。地域史や産業遺産の保存において、中心的な役割を担っている。 ───主な著書── 『日本近世交通史の研究』(1989 吉川弘文館) 『九州・その歴史と現代』(1994 文献出版) 『封建制下の社会と交通』(2001 吉川弘文館) 『参勤交代』(2007 吉川弘文館) 『邪馬台国 魏志が歩いた道』(2009 吉川弘文館) 『前近代日本の交通と社会 ~日本交通史への道1 』(2018 年吉川弘文館) |
|---|